大人にとってはそんなこと。子どもにとっては大ごと(秩序の敏感期2)
おうちでできる&ママができる
モンテッソーリ・ホームスタディの
菅原陵子(りょうこ先生)です。
今日はモンテッソーリ 教育基本のき。
お母さんが一番悩ましく思いがちな秩序の敏感期
を知ったところで、
今日はなんで?というお話に入っていきます
大人にとってはそんなこと。子どもにとっては大ごと
敏感期は、子ども取っては大ごとなのです。
たとえば、こんなことが起きたとき
実例1)
「幼稚園に来るとき工事をしていたのでいつもと違う道を通ったら
ぐずって泣いて、幼稚園に遅刻した」(場所)
実例2)
「Tシャツを洗濯したが 洗ったTシャツを着ると言ってきかず
幼稚園まで振り回して(乾かしながら)来て、乾いたら着た」(もの)
実例3)
「お教室の帰りにパンを買って帰るのだが
いつも買っているパンが売切れで無かったら
突然お店の前で泣き出して大変だった(習慣?モノ?)」
<大人にとっては>
幼稚園に行くなら、どの道を通たっていいじゃない?
=着けばいい
シャツならなんだっていいんじゃない?
=要件が足りていればいい
いつものパンがなければ他のパンだっていいじゃない?
=食べられたらいい。ほかのパンだって楽しみ。
ですよね。
でも、
<子どもにとっては>
要件が満たされたらいいのではなくて
「これでなければならない!!」のです。
ぴったり、いつもと、完全に同じ。がいいのです。
どうして「いつもと同じ」がいいの?
子どもたちは0歳からだいたい3歳くらいまで
見たもの、聞いたもの、触ったものetc 五感を使って
自分の世界を作っていきます。
(くわしくは → 3歳までのお母さんにできること)
それはまるでカメラのシャッターを切るように
1枚1枚、すべてのシーンを、体感を伴って
ため込んでいっているようなもの、と言われています。
だから、ちょっとした違いが違和感になりえるのです。
私たち大人でも、
なじんでいる部屋で誰かがいつもと置き場所を少し変えたら
わかりますよね。
子どもたちの感覚は、その感じがもっと鋭敏。
そして、「仕方ないな」とは思わないのです。
なぜか?
ちゃんと意味があります。
そうやって、子どもたちは
自分たちの世界(環境)を確かめながら
安心安全な場であることを確かめながら
大きくなっていく。
秩序を守ることで、安心して育っていくことができる
その秩序をもって
世界は安心。生まれてきてよかった。
この人は大丈夫な人。ここは大丈夫な場。
それが得られて、はじめて
いろいろチャレンジする子どもになっていく。
そんなところにつながっています
あ!念のために言うと
つながっている、は私の解釈です![]()
でも、毎日ものがころころ変わるところで
気持ちの安定がなかったら、安心安全感は培われないです
これは、どちらかというと、心理学やカウンセリングでの学びを入れた解釈。
いろんなつながりがあって、モンテッソーリってすごいのだな
という理解が深まって行ったり
発達の連続性が腹に落ちたりした部分です。
安心安全は、すべての成長のベースになるもの
前に書いたのは
まだねんねの時期の話として書いていますが
この安心安全は、ベースとしてオヤコでずっと
どんな成長の時期も貫かれている事が
たいせつだと思っています。
そのために、子どもに発達を「予習する」のもおすすめ
そして、子どもの発達を知っておくと
育児はぐんと楽になると思っているので
「予習」って観点、すてきだなあと思います。
ただしね。お母さんが予習して実践するとき
その気持ちのどこかに
「これで抜きんでるこどもになる!!」とか、
「先回りして子どもを伸ばす」というような
コントロールしたい思いが入るととても苦しくなります。
そして
知識を持っていたとしても
たとえば秩序の敏感期だ!と分かったとしても
それは原因が分かっただけ。
どう対処するの?がお母さんの知りたいところじゃないかな。
と思ったりするのです。
モンテッソーリ・ホームスタディはそこを目指しています。
***********
敏感期のお話はこちらも
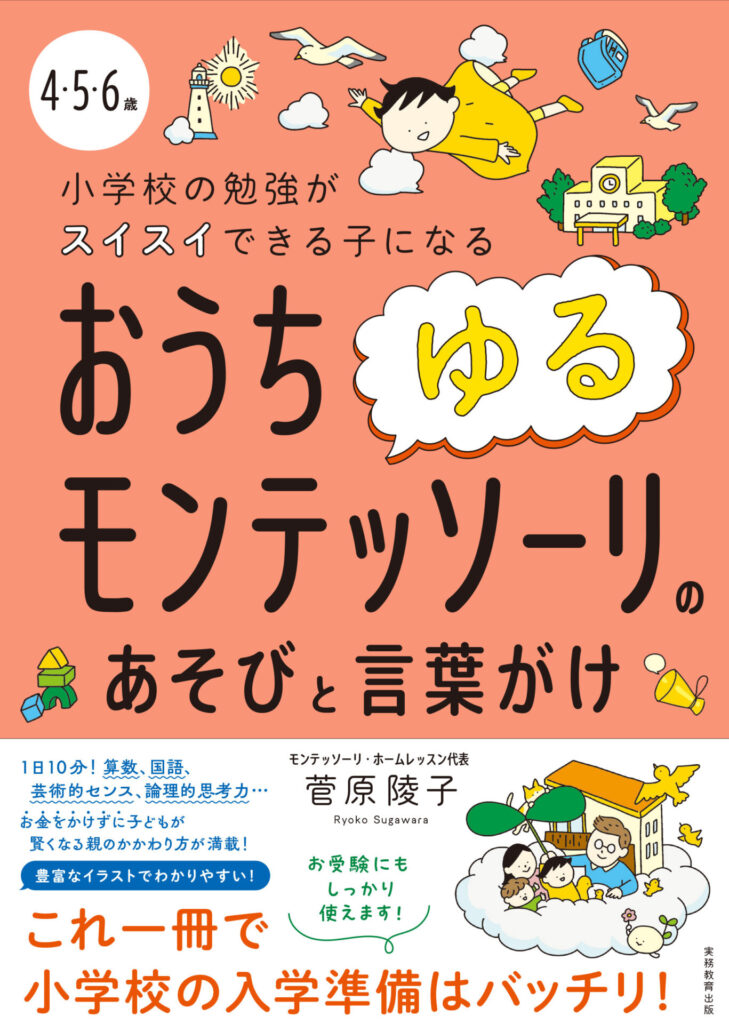
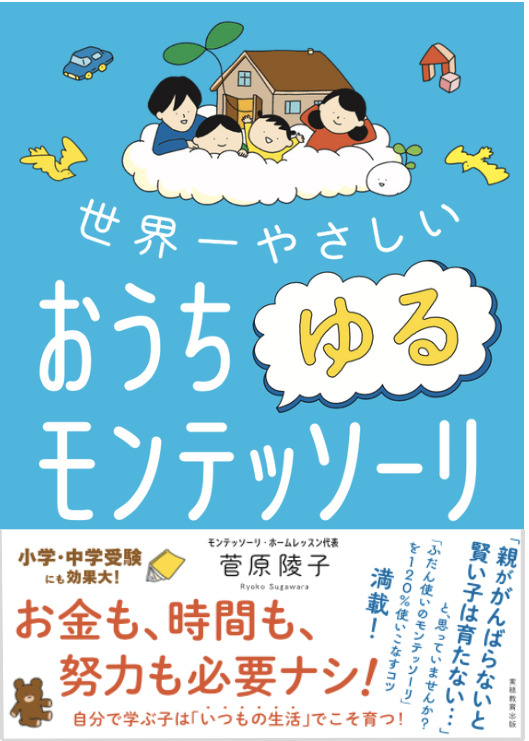



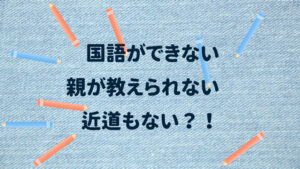
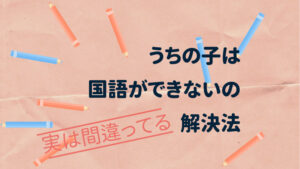


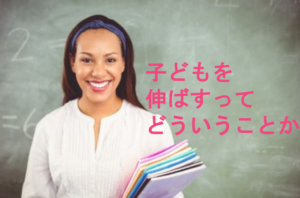

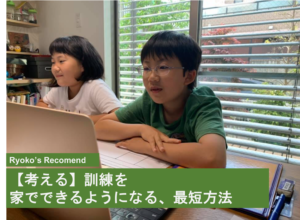

コメント